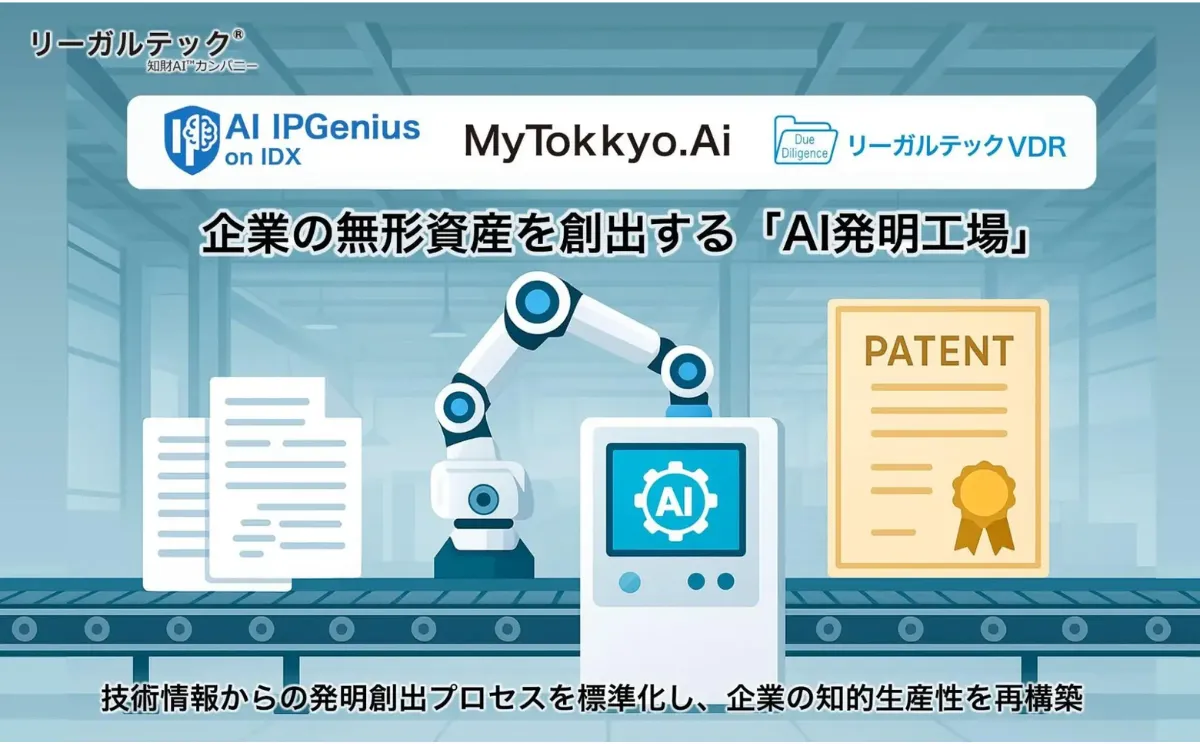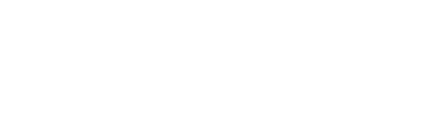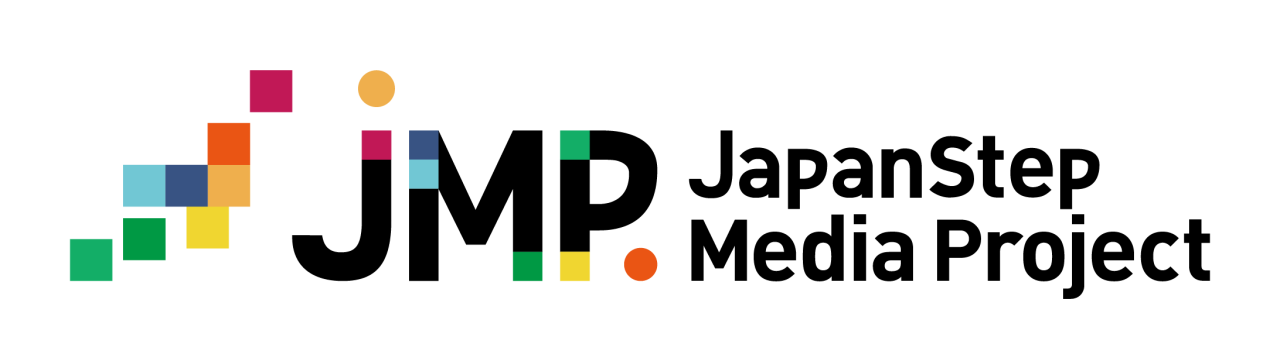- 総合TOP
- 宇宙
- AI
- ロボット
- WEB3・メタバース
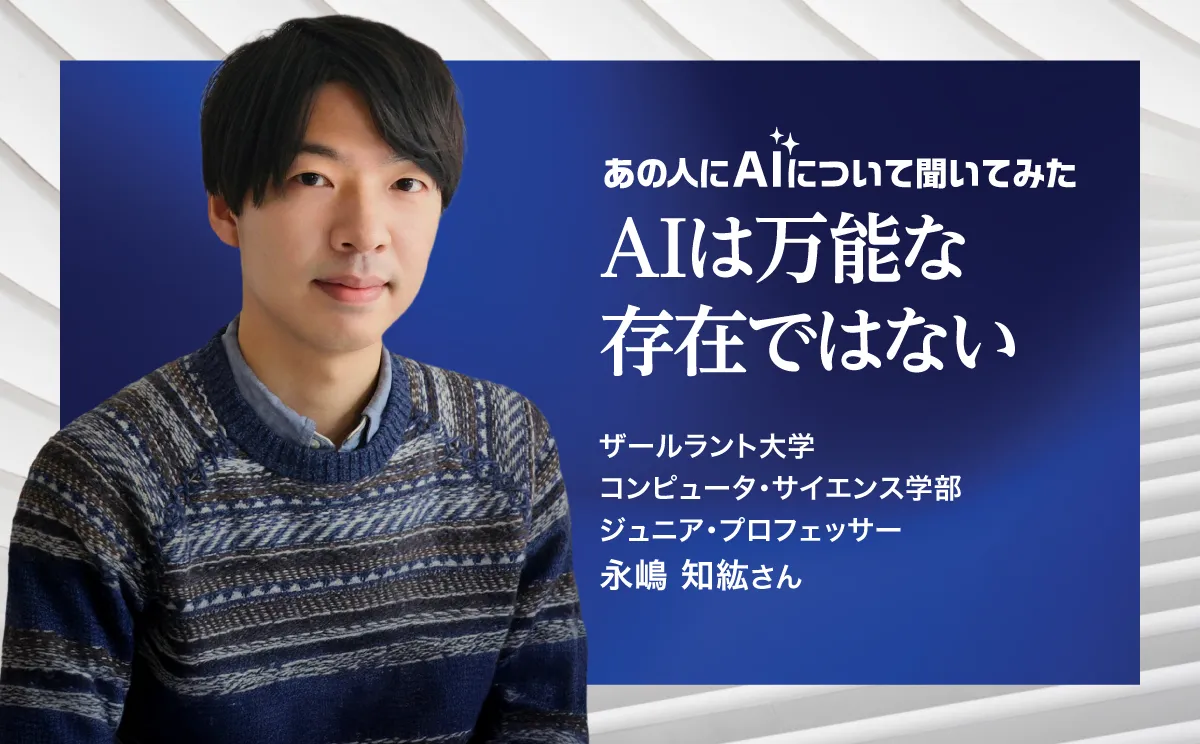
AIの進化は、ビジネスのみならず教育の現場にも確実に影響を及ぼし始めている。では、研究と実践の最前線に立つ研究者は、AIとどのように向き合っているのか。AI Baseの連載「あの人にAIについて聞いてみた」では、一人ひとりの実践と思考を通じて、AI活用のヒントを探る。今回は、ドイツ・ザールラント大学でAI×教育を研究する永嶋 知紘さんに話を聞いた。(文=AI Base編集部)
お話を聞いたのは

ザールラント大学
コンピュータ・サイエンス学部ジュニア・プロフェッサー
永嶋 知紘さん
奈良県生まれ。国際基督教大学(ICU)教養学部卒業。2014年6月から2016年8月まで北海道大学 高等教育推進機構オープンエデュケーションセンターで特定専門職員として勤務。2016年から2017年にかけてスタンフォード大学教育大学院で修士課程、2017年から2022年までカーネギーメロン大学で博士課程研究員として研究に従事。2022年8月に同大学から博士号を取得後、2022年9月よりハーバード大学 Berkman Klein Center for Internet & Societyのファカルティ・アソシエイトに着任。2022年11月から現職。
教育現場に現れた「第三の存在」としてのAI
生成AIの急速な普及により、教育現場でのAI活用は世界共通のテーマとなった。ザールラント大学でジュニア・プロフェッサーとして研究を行う永嶋 知紘さんは、AIを単なる便利なツールとしてではなく、教育空間に新たに加わった「第三の存在」として捉えているという。
「教育現場でAIをどう使うかは、もはや避けて通れない議論になっています。ただ便利だから使う、という話ではなく、どうすれば効果的で、かつ倫理的に使えるのか。データプライバシーの問題も含めて、これまでのテクノロジーとは違う慎重さが求められています」(永嶋さん)
永嶋さんが指摘するのは、AIが教師と生徒の二者関係の間に入り込み、あたかも意思を持つ存在のように振る舞い始めている点だ。研究の現場では、こうした性質を「エージェント」と呼び、従来の教育技術とは異なるものとして位置づけている。
「先生と生徒の間に、もう一人いるような感覚が生まれている。だからこそ、現場の先生方と対話しながら、AIを使ったツールを一緒に設計していくことが重要になります。研究室で作ったものをそのまま持ち込むのではなく、現場の肌感覚に合う形に落とし込む。それが今の私の仕事です」(永嶋さん)
AIを巡る受け止め方には国ごとの差も大きい。カーネギーメロン大学で研究していた米国では、生成AI以前から、学習者の理解度に応じて教材を出し分ける「個別化学習」の仕組みが広く使われてきた。一方、日本やドイツでは、そうしたAI活用の蓄積が十分でないまま、生成AIと出会うケースが多いという。
「アメリカでは、学校現場でもAIを使ったソフトがカリキュラムレベルで導入されていて、話が早い。一方、日本やドイツでは、一人一台端末がようやく行き渡った段階で、いきなり生成AIと出会う。その結果、『AIは怖いもの』という印象から入ってしまうことも少なくありません」(永嶋さん)
永嶋さんは、生成AIを決して特別視しすぎない姿勢も重要だと語る。
「研究分野では、知的学習システムと呼ばれるテクノロジーに代表されるように、学習者を支援するAI技術は長く研究されてきました。生成AIは、その延長線上に現れた新しいタイプのAIです。コントロールの難しさはありますが、過去の蓄積と切り離して考えるべきではありません」(永嶋さん)
教育におけるAI活用は、恐れるか受け入れるかという二択ではない。連続した技術進化の一部として冷静に捉え、現場とともに設計していく姿勢が求められている。
思考を支える相棒としてAIと付き合う
研究者としてAIと向き合う永嶋さんだが、日常生活での使い方は実践的だ。仕事では、ドイツ語でのメール作成や重要文書の下書きなど、言語の壁を越えるためにAIを活用している。
「ドイツ語はまだ十分ではないので、重要なメールを書くときはAIに助けてもらっています。自分の考えを正確に伝えるための補助として使っていますね」(永嶋さん)
プライベートでは、中学生の息子の学習支援にもAIを取り入れているという。
「ドイツの学校では毎週のようにテストがあるので、親のサポートも必要になります。ただ、私たちがドイツ語で教えるのは難しい。そこでAIに練習問題を作ってもらったり、予習用の教材を用意してもらったりしています」(永嶋さん)
その効果は、想像以上だったという。
「正直、私が教えるよりも効率が良くて、子ども自身も前向きに取り組んでいます。楽しみながら学習している様子を見ると、AIは家庭教師のような役割も果たせると感じます」(永嶋さん)
AIを使いこなせていない人へのアドバイスを尋ねると、永嶋さんは「乗り遅れないこと」という言葉を挙げた。
「次の世代は、AIを当たり前に使う世代になると思います。息子を見ていても、それを強く感じます。だからこそ、食わず嫌いをせず、まず触れてみることが大切だと思います」(永嶋さん)
もっとも、無条件に使えばよいというわけではない。プライバシーや情報管理への配慮は欠かせないと強調する。その上で、使いどころを見極める姿勢が重要だという。
「研究のアイデアをAIに考えさせることはしていません。そこは人間が担うべき部分というか、私が自分のアイデアでチャレンジしていきたい部分です。一方で、翻訳や文章の下書きなど、効率化できる作業はAIに任せる。その分、自分の頭を本当に使いたいことに集中できるようになります」(永嶋さん)
AIは万能な存在ではない。しかし、適切な距離感で付き合えば、思考を支える強力な相棒になる。その姿勢は、研究者だけでなく、すべてのビジネスパーソンや学生にも通じるものだろう。
【AI活用のヒント】
・AIは「第三の存在」。恐れるのではなく、現場や目的に合わせて設計する視点が重要
・翻訳や文章作成など、効率化できる身近な作業から試し、役割分担を明確にする
・次世代はAI活用が前提になる。乗り遅れない意識で、まずは触れてみることが第一歩