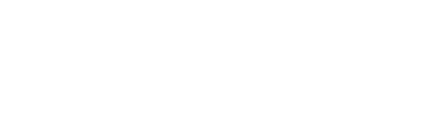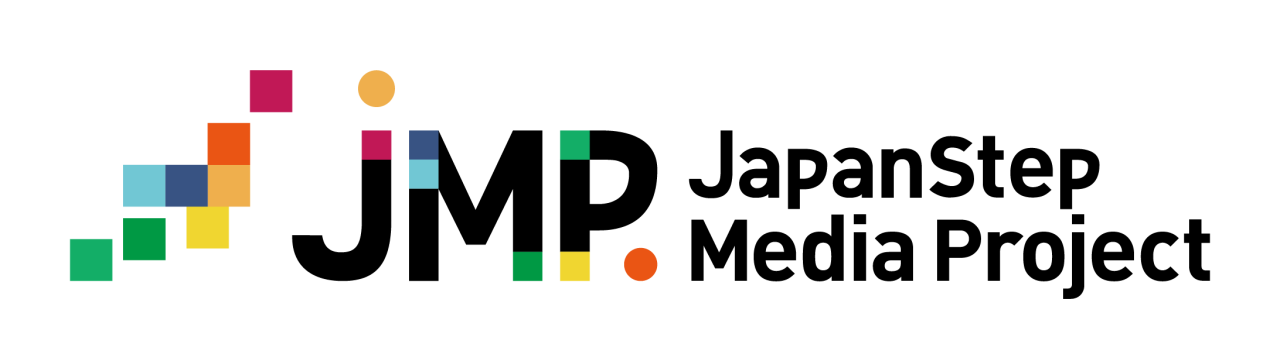- 総合TOP
- 宇宙
- AI
- ロボット
- WEB3・メタバース
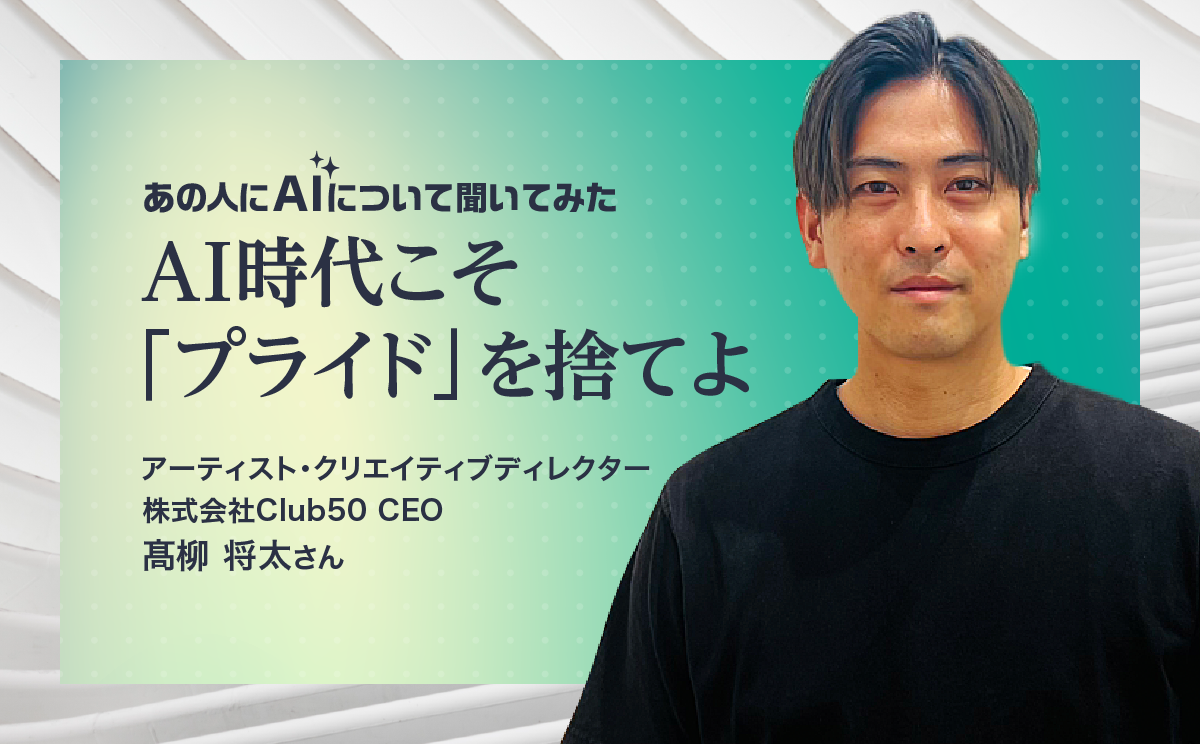
AIはクリエイティブな仕事や学習のあり方も急速に変えつつある。AI活用を多様な視点で学ぶことを目的とする本連載では、様々な分野のプロフェッショナルにAIとの向き合い方や活用術を聞く。今回は、映像制作やアート活動を通じて「目に見えないもの」の可視化を追求するアーティスト・クリエイティブディレクターの髙柳 将太さんに、自身の具体的な活用術から、AI時代に人間が持つべき心構えについて聞いた。(AI Base編集部)
アーティスト・クリエイティブディレクター / 株式会社Club50 CEO
髙柳 将太さん
1986年7月23日生まれ、愛知県出身。アートとデザイン、そして映像表現を横断しながら、企業やブランド、個人の「本質」を可視化するクリエイティブディレクター。映像監督として100本以上のCM・MVを手掛けた経験を基盤に、近年はアートディレクションやブランディング、アパレルなど多様な領域へと活動を拡張。アーティストとしても、絵画・書・写真・映像などを通じて独自の世界観を発信。「アートで世界をつなぐ」をビジョンに、言葉や文化の垣根を越え、アートと社会、個と企業をつなぐ新たな表現の形を生み出している。
これからの注目はAIが何と紐づくか
AIの進化に注視し、かなり早い段階からAIに触ってきたというアーティスト・クリエイティブディレクターの髙柳 将太さんは、「かなり高い完成度まできている」と進化のスピードに驚いているという。そのうえで、今後はAIそのものの性能向上よりも、「何と紐づくか」に焦点が移ると分析する。AIをどのようなプロセスや人間の思考と結びつけるかによって、その成果は大きく変わる。単に便利なツールとして使うのではなく、創造のプロセス全体に組み込み、知的生産の「拡張装置」として使うことが鍵だという。
髙柳さんは、AIを積極的に活用するクリエイターの一人だ。例えば、専門性が高く、かつ自分の専門領域ではない書籍を読む際にはChatGPTを活用。「わからない単語が出たら、小学生にもわかるように短く説明してください」と音声で指示を出す。難解な専門書でも、文脈を崩さず要点を整理できるので、理解のスピードが格段に上がるという。AIを通して得られるのは単なる知識ではなく、情報の構造を把握する力だ。髙柳さんにとって、AIは「思考の地図」を描くナビゲーターのような存在だと位置づけている。
また、映像制作の現場でもAIを導入している。1時間におよぶインタビュー映像を文字起こしさせ、チャプター分割やタイトル案を生成するのが日常的なフローだ。AIを下支えとして使うことで、編集作業の初期段階を大幅に短縮できる。さらに、素材のトーンや語彙の傾向を分析させることで、構成の方向性を見極める参考にもしている。一方で、「構成の再構築や物語の流れを設計するような高度な編集判断までは任せられない」とも語る。AIが得意とするのは、整理・要約・パターン抽出の領域であり、感情や意図を読み取る段階では人間の感性が不可欠だ。
AIには具体的なタスクを担わせ、自身はより抽象度の高い判断に集中する。その明確な役割分担が、AI時代の生産性向上に直結している。「AIは思考の前段を整理してくれる存在。だからこそ、私たち人間は、発想や構想、意味づけに時間を使うべきだと思います」と語る。実際、AIの導入によって単に作業効率が上がるだけでなく、思考の質そのものを高める余白が生まれたという。
さらに髙柳さんは、AIの精度を引き出すための「問いの立て方」にも工夫を重ねている。「AIに正しい答えを求めるのではなく、AIと一緒に問いを深める」というスタンスだ。具体的なアウトプットを出す前に、前提条件や論点をAIと対話的に整理することで、より多角的な視点を得られる。これは人間同士の議論に近く、AIを「思考の触媒」として使うアプローチだ。AIの回答から「想定外の切り口」を見つけることが、次の発想へとつながる。「AIを使うほど、自分の『思考の癖』が見えてくる。それを自覚できること自体が、AI時代のリテラシーだと思います」と語る。
時代を乗りこなす鍵は「プライドを捨てる」こと
AI活用において、髙柳さんが重視するのは「余計なプライドを持たない」姿勢だ。「ChatGPTはすぐに使えたが、実は映像のAIはすぐに取り入れられなかった。正直、自分の技術におごっていた部分もあったからだと思います」と率直に語る。人は自分の得意領域に新しい技術が入り込むと、無意識に防衛反応を起こし、否定から入ってしまう。しかし、その心理こそがAI活用の「壁」になるのでは、と指摘する。
髙柳さんは、「AIを拒む気持ちの中に、AIが自分の専門性を脅かすと感じている点があると思うが、実際には逆だ」と語る。高柳さんが主張するのはAIが「代替者」ではなく、「拡張者」であるという視点だ。プライドを手放し、未知の技術に柔軟に向き合うことで、AIは人間の能力をより深く掘り下げるための鏡となる。高柳さん自身もかつて、AIによる映像生成を「感覚的に合わない」と感じたが、意図的に使い続けるうちに、表現の解像度が上がっていく感覚を得たという。
また、AIの最大の価値は「自分の聞き方で質問できる」点にあると強調する。これまで教育は、教師や教材が提示する「正解」を前提に進んでいた。しかしAIとの対話では、問いの質そのものが学びの深さを決める。AIがもたらす個別最適化された学習環境は、これまでの一律的な教育構造を覆す可能性を秘めている。髙柳さんは「何かの分野において、大人が子どもに頭を下げて教えてもらう時代が来るのでは」と、新しい未来を見据えた。
髙柳さんが最も重視するのは、AIには決して到達できない領域──「自分の内側にある声」、つまり直感や本能の探求である。データと論理で導かれるAIの世界に対し、人間には「感じる力」が残されている。髙柳さんは毎朝30分から1時間の瞑想を欠かさない。呼吸を整え、五感を研ぎ澄まし、心身が「気持ちいい」と感じる方向を選び取る訓練を続けることで、本能的な判断力を養っているという。「AIが効率や正解を提示する時代だからこそ、非合理の中にこそ真実がある」と語る。直感を信じる力、そしてそれを表現につなげる感性こそ、人間にしか持ち得ない創造性の源泉なのかもしれない。
【AI活用のヒント】
・AIは「整理と構造化」の支援者。効率化ではなく、思考の深度を高めるために活用せよ
・AI時代こそ固定観念やプライドを手放し、好奇心と柔軟性をもって技術と向き合う必要
・AIが扱えない「感情」「偶然」「美意識」にこそ、人間の創造力が宿る