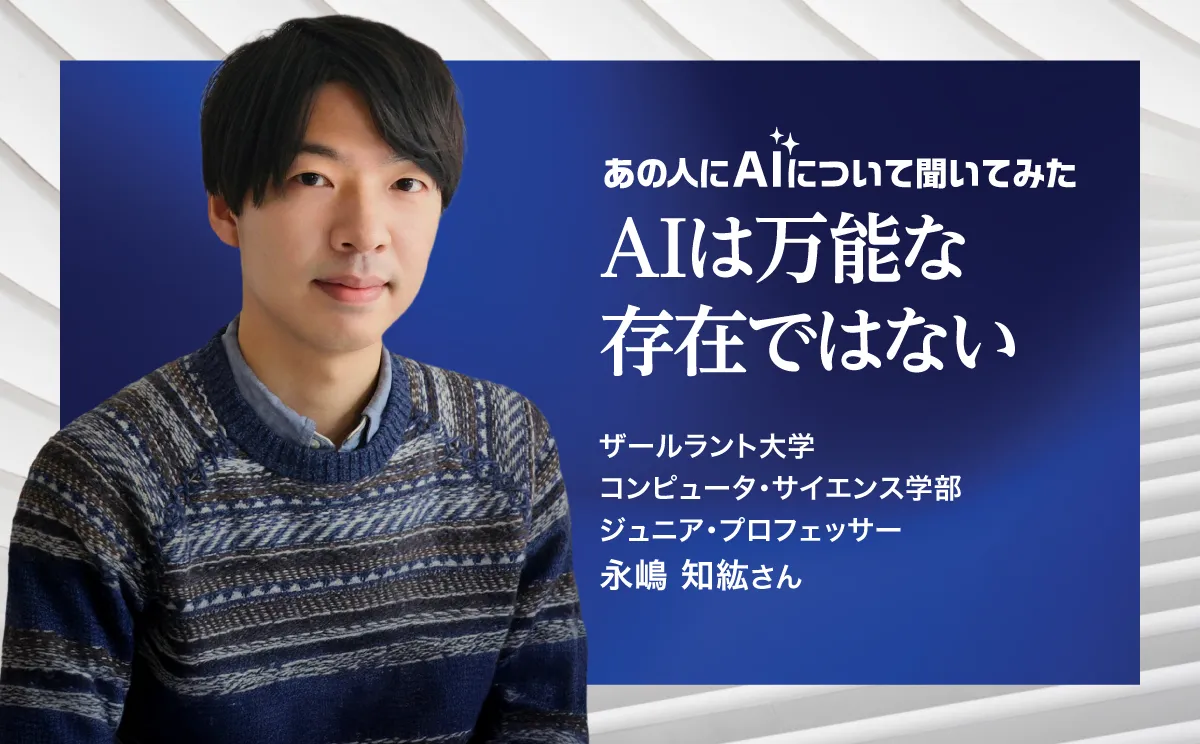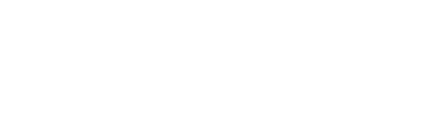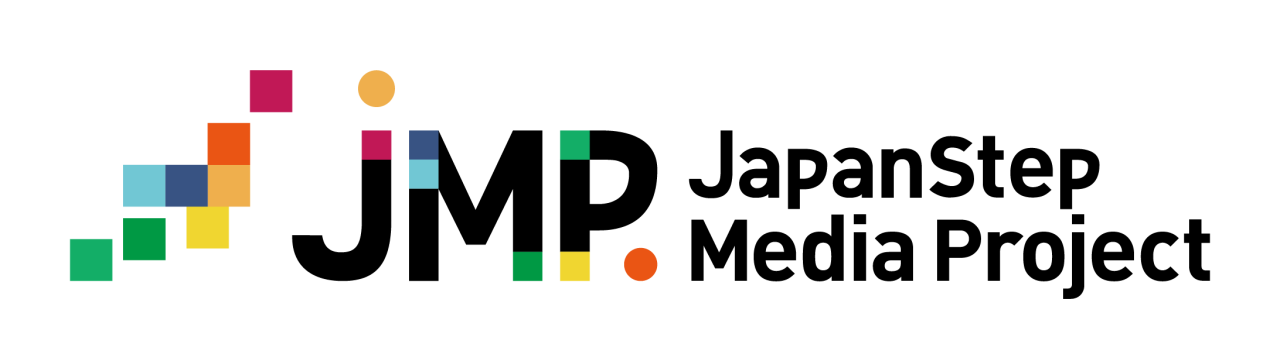- 総合TOP
- 宇宙
- AI
- ロボット
- WEB3・メタバース

連載「NEXT GEN~原石たちの挑戦」では、日本を共創でステップさせるために若き挑戦者たちの発想と行動力からこそ学びがあると考え、活躍する若い世代のインタビューをお届けしている。今回登場いただいたのは、和歌山大学 観光学部に在籍する大学2年生。宇宙と観光を結びつける視点で地域の未来を描く清野 健太郎さんだ。本州最南端に位置する和歌山県串本町は、日本初の民間ロケット発射場「スペースポート紀伊」を擁し、宇宙ビジネスの新たな拠点として注目を集めている。幼少期から星空を仰ぎ見て育ち、高校時代には「缶サット甲子園」やロケット打ち上げの生配信に挑戦してきた清野さん。地域の課題を直視しながらも、宇宙と観光を重ね合わせた挑戦を続ける彼の姿から、次世代が描く地域の可能性を探る。(文=JapanStep編集部)
豊かな自然と課題の狭間で~宇宙に託す地域の希望
和歌山県串本町は、本州最南端に位置し、三方を山と海と川に囲まれた自然豊かな町である。幼少期をこの地で過ごした清野 健太郎さんは、自然と触れ合う日々を送り、伸びやかに育った。「串本町は、海も山も川もある本当に自然豊かな場所なので、親の方針で基本的に家の外で遊べという教育方針でした」と清野さんは笑う。

和歌山大学 観光学部
清野 健太郎さん
和歌山県串本町出身。星空がキレイな山・海・川に囲まれた自然の中で育つ。和歌山県立串本古座高校在学中には「缶サットプロジェクトチーム」を立ち上げ、ロケット初号機「カイロス」打ち上げ時には高校公式YouTubeで生配信し、注目を集めた。現在は和歌山大学 観光学部で学びながら、串本町の広報活動やツアーガイドなどを通じ、宇宙と観光の可能性を探究している。(写真提供=清野 健太郎さん)
和歌山県串本町は、本州最南端に位置し、三方を山と海と川に囲まれた自然豊かな町である。幼少期をこの地で過ごした清野 健太郎さんは、自然と触れ合う日々を送り、伸びやかに育った。「串本町は、海も山も川もある本当に自然豊かな場所なので、親の方針で基本的に家の外で遊べという教育方針でした」と清野さんは笑う。
中学校は全校生徒が15名、同級生はわずか5人という小規模校で、家族のような仲間との密度の濃い時間が人とのつながりを重んじる価値観を育んだ。高校に進学し、同級生の数が一気に増えた環境を経験した清野さんは、自らの関心分野に挑戦できる機会を得た一方で、地域社会の現実にも直面する。同級生の多くが「地元には就職先がない」と口にし、将来は町を離れざるを得ないと考えていたのである。高齢化の進行や人口減少は顕著であり、地域に根ざした産業や雇用の不足は、次世代の定着を阻む大きな壁となっていた。
そうした中、清野さんの宇宙への関心が現実と結びついたのは中学1年時に遡る。串本町に日本初の民間ロケット発射場「スペースポート紀伊」が建設されるというニュースが飛び込んできた。それまで星空を眺める存在だった宇宙が、突如として自らの町からロケットが飛び立つ「現実」へと変わったのだ。清野さんは「まさか自分の町にロケットが打ち上がるなんて信じられなかった」と当時を振り返る。
高校時代、彼は宇宙への夢を行動に移す。空き缶サイズの模擬人工衛星の技術力・創造力を競う大会である「缶サット甲子園」にチームを結成して挑み、3年間にわたり試行錯誤を重ねた。結果は失敗の連続であったが、その過程で「成功と失敗を二分するのではなく、どこまで達成し、どこから課題が残ったのかを冷静に見極める」思考を身につけたと語る。

「缶サット甲子園」の様子(写真提供=清野 健太郎さん)
また、2024年3月のロケット初号機「カイロス」打ち上げ時には、地元住民や全国の人々が半信半疑の中で「現実の出来事」であることを伝えるべく、高校公式YouTubeでの生配信を企画。緊張しながらも実況を務め、その映像は大きな反響を呼んだ。清野さんは「活動を継続的に見守っていただく人々の存在を実感しましたし、改めて串本町にとって大きな出来事であることを実感しました。増えたフォロワー数としての数字は小さいかもしれないですが大きな手ごたえを感じました」と振り返る。
打ち上げを契機に、串本町の宇宙への取り組みは、さまざまな形で広がる。清野さんの母校には全国初となる公立校の「宇宙探究コース」も設立された。こうした活動を経て、清野さんの胸には「自然豊かな故郷を次世代につなげたい」という思いが強く芽生えた。観光を切り口に、宇宙を活用して地域を盛り上げる――清野さんの挑戦への思いはより強いものとなっていく。
宇宙観光がもたらす経済効果と持続可能性の課題
大学進学後、清野さんは観光を専門的に学びながら、串本町における宇宙関連の広報活動も続けている。宇宙服を着て、地元で開催される宇宙関連のイベントで司会を務めたり、地元企業と協働したバスツアーに参画したりするなど、観光資源としての「宇宙」の可能性を広く発信してきた。
実際にバスツアー参加者からは「もう一度見たい」「次も必ず来たい」といった声が相次ぎ、ロケット打ち上げは強いリピーター需要を生み出している。打ち上げ延期の際にも「また来ました」と足を運ぶ観光客が少なくないことからも、宇宙が観光資源として独自の魅力を放つことが裏付けられる。清野さんは「スペースポート紀伊は、本州にあり実際に訪れることができる点で、観光資源としても大きな可能性を感じます」と分析する。
 2024年3月に開催されたロケット見学場の様子(写真=PRTIMES 串本町リリース)
2024年3月に開催されたロケット見学場の様子(写真=PRTIMES 串本町リリース)
この動きは地域経済にも波及している。地元の飲食店や土産物店では「ロケットカレー」といった宇宙関連商品の開発競争が始まり、観光を契機とした新たな創意工夫が芽吹きつつある。一方で、地域内循環の仕組みが十分でない課題もある。観光客が購入する商品の多くが地域外で製造されているため、売上が町外へ流出している現実もある。清野さんは「地域内で生産し、地域外へ届ける仕組みを整えることで、経済効果を持続させる必要がある」と強調する。
 「自然豊かな串本町の魅力を是非現地にきて感じて、見つけてほしい」と清野さんは語る
「自然豊かな串本町の魅力を是非現地にきて感じて、見つけてほしい」と清野さんは語る
さらに、観光学を学ぶ立場からはオーバーツーリズムへの警戒感も示す。過剰な観光客流入は交通や環境への負荷を高め、地域の生活を圧迫する危険性を孕む。京都や鎌倉での事例を引きながら「観光が地域を消費する負の側面を避けるには、計画的かつ専門的な観点からのマネジメントが欠かせない」と語る。
清野さんは今後、国内外の他地域における観光の事例を学び、自らの視野を広げたうえで、必ず串本町へ帰郷し地域に貢献したいと展望を描く。清野さんにとって観光とは、単なる交流産業ではなく、地域を守り、未来へつなぐための戦略的手段である。
「初めて来た人には『何もない』と思われるかもしれないが、実は『ここにしかないもの』が数多くある町です。だからこそ、串本町を訪れてその人なりの魅力を見つけてほしい」と清野さんは語る。次世代の挑戦者が描くのは、宇宙がもたらす地域活性の青写真だ。串本町が「最南端の町」から「宇宙の玄関口」へと変貌していく未来。そこで若い世代が活躍する未来は、すでに現実の射程に入っている。

橋杭岩から見た打ち上げイメージ。スペースポート紀伊では、スペースワン株式会社運用のもと、
2020年代に年間20機の打ち上げが計画されている(写真=PRTIMES 串本町リリース)
取材を終えて
串本町に育ち、地域の魅力と危機感を誰よりも感じ、意欲的に観光を学び、活動をされている清野さんの言葉は説得力の塊でした。スペースポートによる経済効果や地域に与えるプラスの効果は間違いなくあるでしょう。だからこそ、地域主体で戦略的に取り組むことやそこに若い世代の活躍も欠かせないことを痛感しました。取材の最後には、宇宙ビジネスを身近にするWEBメディア『SpaceStep』での連載に携わってくれると意欲的に語ってくれた清野さん。清野さんのご活躍はもちろん、ご一緒に、「宇宙×観光」を盛り上げていけることを楽しみにしています。
併せて読みたい
大学生活や勉学などでAIを使いこなしているという清野さんに、AIの進化に対する考え方と日常的な活用法を聞いたコラム 「AIで大学生活がアップデートされました~【連載】あの人にAIについて聞いてみた」もご覧ください。