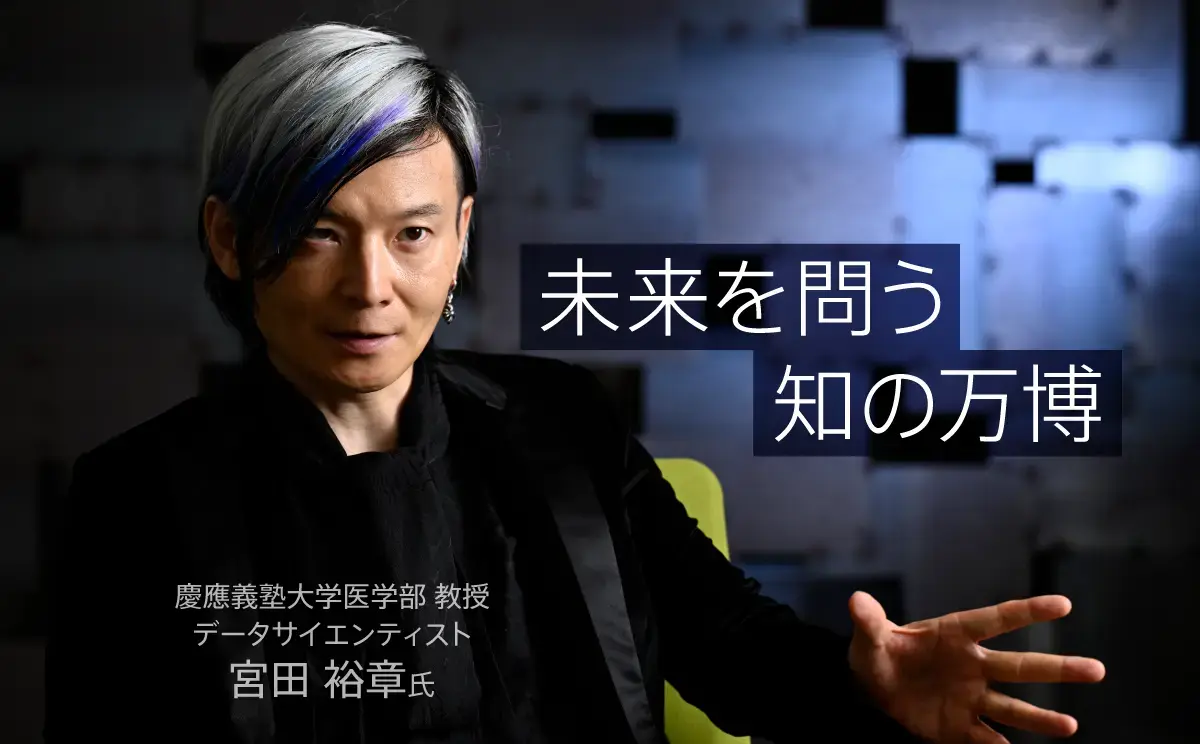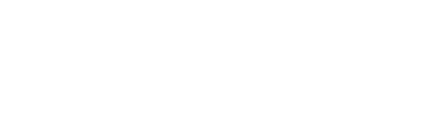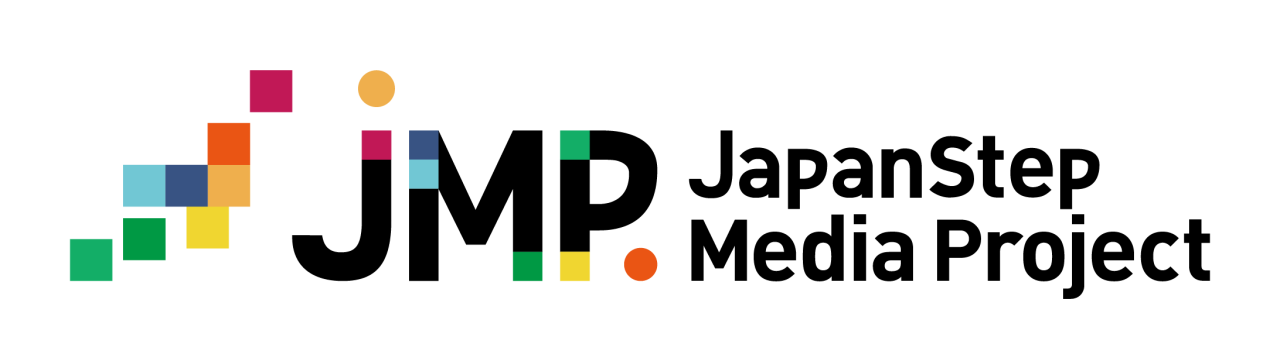- 総合TOP
- 宇宙
- AI
- ロボット
- WEB3・メタバース

AppleやGoogle、Intelなど世界的なIT企業だけでなく、あらゆる産業の集積地として知られるアメリカ。その規模感、技術の先進性など、目指すべき指標となる企業が集まっている。最先端テクノロジーのトレンドや考え方を知ることで、日本におけるビジネスパーソンにヒントを得て欲しい。このたび、シリコンバレーやホワイトハウスなど、米国のトップ層での経験が豊富な戦略アドバイザー、ペイトン・イヒミ氏に、テクノロジーに関するコラムをご寄稿いただくことに。記念すべき第1回はAI設計。シリコンバレーのリアルな温度感を知るペイトン氏から、AI設計・活用で見落としがちなポイントも含めた考えを語っていただいた。

ペイトン・イヒミ(Nkechi "Payton" Iheme)
グローバル政策および政府関係、官民連携、ソーシャルインパクト、CSR の専門家。政府機関からFacebook、Bumble、Intrepid Travelなどで要職を歴任し、国際交渉や資金調達を主導。多国籍企業や政府と協働し、社会的インパクトとテクノロジーの推進に尽力している。
シリコンバレーの盲点から学ぶ——AIをより賢くつくるために
ソーシャルメディアが急成長を遂げた時代、シリコンバレーはスピードと創造性に満ちあふれていました。一方で、社会的なインパクトへの理解や配慮は、技術の進歩に追いついていない場面もありました。多くの課題は悪意によるものではなく、「広い視野を持たないままスケールしてしまった」という構造的な背景に起因しています。
今、私たちは再び同じような局面に立っています。生成AIの進化は目覚ましく、私たちの日常や社会の根幹に影響を与えつつあります。ここで重要になるのは、「何をどう作るか」に加えて、「誰がその方向性を決めるのか」という問いです。
私はこれまで、政府、グローバルテック企業、国際開発機関などで政策とテクノロジーの接点に関わってきました。AI活用の倫理・責任ある推進を目指す国際的業界団体Partnership on AIの立ち上げにも参画し、AIの安全性や倫理に関する国際的な議論に携わってきた経験から言えることがあります。それは、AI開発において、「早く作ること」よりも、「何を優先して作るか」を明確にすることが、これからの時代に求められているということです。
スピードだけでは戦略にならない
ソーシャルメディアの初期は、「どれだけ多くの人をつなげられるか」「どれだけスムーズに動作するか」に注力されてきました。その結果、信頼性や包摂性といった重要な要素が十分に議論される機会は限られていました。
生成AIも同様に、急速な進化を遂げています。しかし、スピードそのものが戦略ではありません。何かを作ることができるからといって、すぐに作るべきとは限りません。文脈や影響、責任について深く議論することが必要です。
これは開発を遅らせるべきという話ではありません。「どこへ向かっているのか」を明確にした上で進むことが求められているのです。
最適化と整合性はイコールではない
ソーシャルメディアの成長期、成功は「エンゲージメント」で測られてきました。クリック数やシェア数が多ければ多いほど良いとされていました。しかし、その結果として、誤情報や対立が助長されるケースもありました。
生成AIでは、「確率的にもっともらしい」出力が最適化されていますが、それが常に正確・安全・有益であるとは限りません。だからこそ、開発の初期段階から整合性や安全性、外部による評価の仕組みを取り入れる必要があります。
透明性が信頼を生む
過去のテクノロジーの教訓のひとつに、「仕組みが見えないと人々は不信感を抱く」というものがあります。アルゴリズムの判断理由が不明だったり、コンテンツの表示優先度が突然変わったりすると、ユーザーはその変化に置いていかれてしまいます。
AI、とくに大規模言語モデルのようにブラックボックス化しやすい技術においては、透明性の確保が極めて重要です。それは技術文書にとどまらず、現実社会での使われ方まで含めて明示される必要があります。独立した研究機関との連携や、社会的インパクトに関する事前評価の公開といった取り組みが、今後の信頼獲得において大きな鍵を握ります。
包括性は倫理だけでなく戦略でもある
誰が開発に関わるかということは、製品の設計やリスク評価に直結します。過去のテック業界では、開発チームが同質的であったために、多様なユーザーの視点が抜け落ちてしまうことがよくありました。
AIでは、過去のデータに基づいて学習するモデルが多く使われており、過去のバイアスや盲点が無意識のうちに反映されるリスクがあります。そのため、女性、高齢者、神経多様性のある方、テクノロジーの恩恵を受けにくかったコミュニティなど、さまざまな立場からの視点を初期段階から取り入れることが不可欠です。
それは公平性を担保するためだけではありません。柔軟で強靭な、そしてグローバルで通用するシステムを構築するための戦略でもあるのです。
責任は法規制よりも早く始まる
過去のテクノロジーの潮流では、「まずは規制を待とう」という姿勢が一般的でした。しかし、その間に信頼が失われてしまった事例も多くあります。
現在、各国政府がAIの法整備に取り組んでいることは重要ですが、先進的な起業家や企業は、すでに自主的なルールづくりに取り組んでいます。フィードバックを受け入れ、自社の原則を明示し、ローンチ前にシステムを検証する。このようなガバナンスの姿勢は、倫理的に優れているだけでなく、ビジネスとしての信頼性を高めるシグナルにもなります。
日本がリードできる可能性
幸いなことに、私たちはゼロから始める必要はありません。日本には、「精度」「配慮」「長期視点」といった文化的な土台があります。これらの文化的直感ともいうべきソフトパワーは、未来のAIを形作るための強力な競争優位となり得ます。
シリコンバレーの道をそのまま追うのではなく、何を引き継ぎ、何を進化させるかを意図的に選ぶことができます。一部の起業家はすでに、信頼性、プライバシー、社会的インパクトについて深く考えはじめています。こうした姿勢が、新しいリーダーシップのかたちとなり、目的を持ったイノベーションへとつながるのです。
長期視点で構築するということ
AIは単なるプロダクトではなく、すでに社会のインフラの一部になりつつあります。働き方、学び方、意思決定のしかたにまで影響を与えています。
だからこそ、何を作るかだけでなく、「なぜそれを作るのか」という視点が不可欠です。その背景にはどのような前提があるのか、誰が取り残される可能性があるのか、失敗が起きたときの責任の取り方はどうするのか——こうした問いを避けずに考えることが、企業としての持続性を左右します。
最後に:文化が未来を形づくる
今、若い世代はAIの成り立ちを注意深く見つめています。どのような価値観のもとに、誰がどのような意思決定をしているのか。その過程が、将来のリーダーシップや創造性、そして社会との関係のあり方に大きな影響を与えるでしょう。
私たちが今構築しているのは、単なるツールではありません。新しい文化の基準そのものです。もし今、明確な意図と包括性を持ってAIを設計することができれば、それは単なる技術革新ではなく、「信頼される未来」そのものを築くことになるでしょう。(次回に続く)